今回は、令和の時代になっても「地域の言葉(方言)は大切に残していきたいですね」というお話しです。
まあ、そう言わず・・
とりあえず・・引き続きお読み下さい。
昭和、平成、令和と時代が変化するとともに、言葉も若者を中心に変化していき、次々と新しい言葉が、生まれは消え、生まれは消えしていますよね。
たとえば・・若者言葉の中で・・
言葉を簡単にして、略語にしたような・・
また・・
語呂合わせというか、ダジャレ?みたいな・・
 (フロリダ=風呂に入るから会話(SNS)から離脱する)
(フロリダ=風呂に入るから会話(SNS)から離脱する)
なんて・・もう古いね・・
おそらく、誰かが新しい表現を使いだして、それがSNSなどで拡散されると、みんな面白がってそれを使い、飽きてくれば、また新しい言葉が出て、そしてまた消えていく・・
若者の流行りの中で、言葉は、出ては消え、出ては消えの時代の言葉・・
それに輪をかけて、大の大人が若者ぶって、若者の言葉を使ったりしますから・・
「ムム・・オレか・・」
それを・・
「日本語が乱れた」ととらえるのか・・
「言葉も時代と共に変化していく」ととらえるのか・・
まあ、どうとらえるかは、人それぞれですが・・
言えることは、多くの現代人は、そんな言葉を使ってコミュニケーションをとっているということです。
若者が流行らせる言葉が次々と変わっていく中で、日本には、変わってほしくない「地域特有の歴史のある言葉」もあります。
それは・・
その地域独特の・・
古くから使われてきた・・
独特なイントネーションの・・
その地域の文化とも言える言葉・・「方言」
ついこの前・・、この前といっても、かなり前か・・
「そだねー」って言葉が話題になりました。
そうそう、あのカーリング女子の選手が使っていた言葉。
そのイントネーションが、なんか、ほっこりして、あたたかくて、親しみを感じたのを覚えています。
これも北海道の方言です。
「そだねー」を、若者に流行っている言葉にするなら・・「それな」に当たるのですかね?
自分が住んでいる長野の田舎でも、方言があって・・
「そだねー」に似たものでは・・
そうせゃあ(そうですよ)
などなど・・
長野県は、南北に長く広い県のためか、方言も地域ごとに微妙に違い、多くの県と接していることもあって、違う県と同じ方言を使っているなんてこともありますねぇ。
田舎では・・
村の中で、ご近所の人を見つければ・・
 よってかねかい(うちに来て、お茶でも飲んでいきませんか?)
よってかねかい(うちに来て、お茶でも飲んでいきませんか?)
なんていう言葉が自然と出る、
いかにも田舎っぽい・・
それを、あいさつ代わりに使ったりしています。
他にも・・
自分の畑で野菜がたくさん採れた・・とか
珍しいものをいただいた時・・とかには・・
 ちっとばかだけん(少しばかりですが、おすそ分けです。)
ちっとばかだけん(少しばかりですが、おすそ分けです。)
という「おすそわけの精神」
 わりぃね(悪いね、いつもありがとう)
わりぃね(悪いね、いつもありがとう)
という、「持ちつ持たれつの精神」
それらが、田舎のあたりまえの日常・・
おそらく都会には、なかなかない事でしょうし・・
さらに・・
令和の時代になれば、新しい技術がますます発達して・・
自動運転だとか・・
5Gだとか・・
VR/ARだとか・・
「AI」なんて人工知能ですよ・・
人工の?・・知能?・・
人間じゃないんですから・・
もうビックリです・・
そんな時代に・・
「・・ずら」なんて言っているのは、不釣り合い?のように見えますが・・
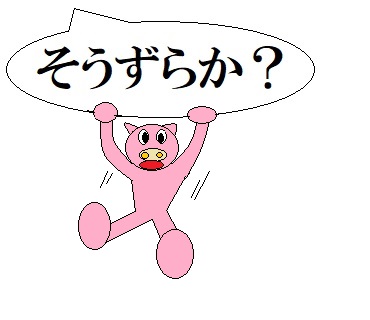 新しい時代なっても大事なのは、ご近所や地域とのつながり・・
新しい時代なっても大事なのは、ご近所や地域とのつながり・・
また、田舎ならではの、地域の仲間意識とか人間らしい精神・・
そんな地域をつなげる「方言」・・
大切なものは、いつまでも残していきたいものです。
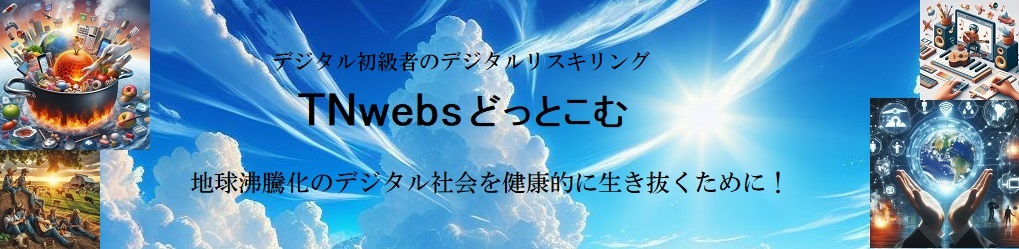


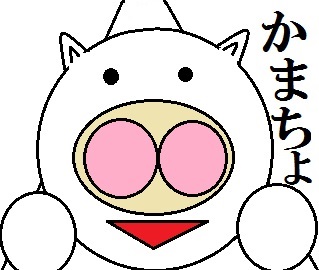
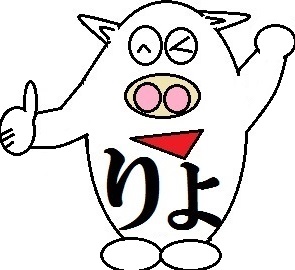

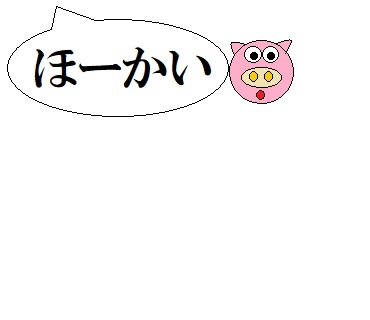

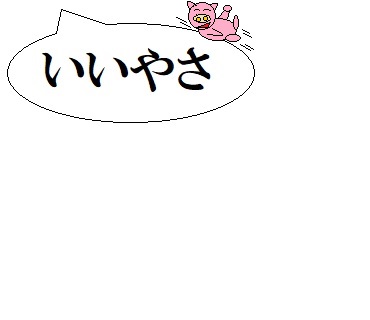


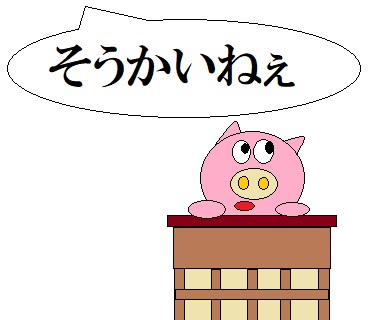


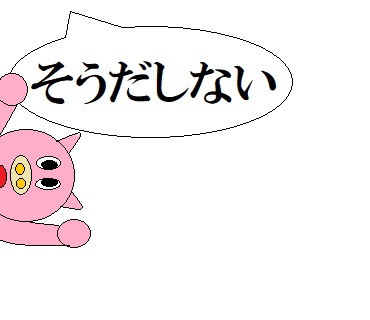

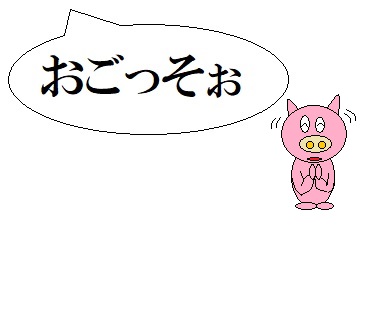


コメント